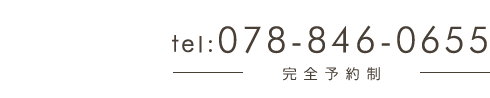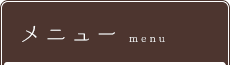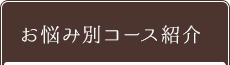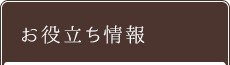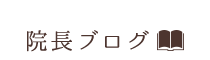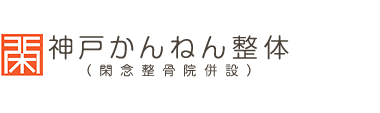「O脚」とは、両足を揃えて立ったときに、膝と膝の間に隙間ができてしまう状態を指します。見た目だけでなく、膝や股関節への負担が増え、将来的なトラブル(変形性膝関節症など)につながる可能性もあるため、予防や改善が大切です。
O脚予防のポイントはいくつかありますが、主なものは以下の通りです。
1. 姿勢の改善
O脚は、普段の姿勢が大きく影響しています。
 正しい立ち方:
正しい立ち方:
- 重心をかかとではなく、足の裏全体で支える意識を持つ。
- つま先を少し外側に向ける(ガニ股にならない程度)。
- 膝を軽く緩める(突っ張らない)。
- 骨盤を立て、お腹を引き締める。
- 頭のてっぺんから糸で引っ張られているようなイメージで、背筋を伸ばす。
 正しい座り方:
正しい座り方:
- 深く腰掛け、骨盤を立てる。
- 足の裏全体を床につける。
- 足を組む癖をやめる。
2. 筋肉のバランスを整える
O脚の人は、内ももの筋肉(内転筋)が弱く、お尻の外側の筋肉(中殿筋など)が硬くなっている傾向があります。これらの筋肉のバランスを整えることが重要です。
- 内転筋の強化:
- 太ももの間にクッションなどを挟んで締めたり緩めたりする運動。
- スクワット(膝を内側に入れないように注意)。
- 開脚ストレッチ。
- お尻の外側の筋肉(中殿筋など)の柔軟性向上:
- お尻のストレッチ(あぐらをかいて体を前に倒す、片膝を抱え込むなど)。
- フォームローラーなどを使って筋膜リリースをする。
3. 足裏のアーチを意識する
足裏のアーチが崩れると、O脚の原因となることがあります。
- 足指を使う意識:
- 足の指でグー・パーをする運動。
- 足指でタオルを引き寄せる運動。
- 靴選び:
- 足に合った、かかとがしっかりした靴を選ぶ。
- クッション性があり、アーチをサポートするインソールを使用するのも有効。
4. 日常生活での注意点
- ぺたんこ座り(女の子座り)をやめる: 膝や股関節に負担がかかり、O脚を悪化させる可能性があります。
- 片足重心で立たない: 左右のバランスが崩れやすくなります。
- 同じ体勢を長時間続けない: こまめに姿勢を変えたり、ストレッチをしたりする。
- 適度な運動: ウォーキングなど、全身運動で体全体のバランスを整える。
5. 専門家への相談も検討する
O脚がひどい場合や、痛みがある場合は、整形外科医や理学療法士に相談することをおすすめします。専門家による評価と、個々の状態に合わせた適切なアドバイスやリハビリテーションを受けることができます。
これらの予防ポイントを日常生活に取り入れることで、O脚の改善や予防に繋がります。焦らず、地道に続けることが大切です。
※ご相談はこちらからお気軽になさってください。
神戸かんねん整体
#股関節痛 #変形性股関節症 #膝関節痛 #変形性膝関節症 #四十肩 #五十肩 #側弯症 #O脚 #慢性腰痛 #座骨神経痛 #脊柱管狭窄症 #頸の痛み #肩こり #頭痛 #足の痛み #脚長差
神戸市東灘区御影中町6丁目4-23エスペランサ御影1F
078-846-0655