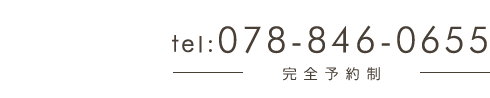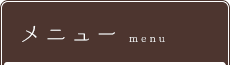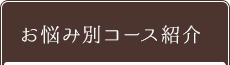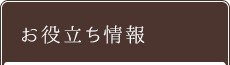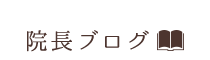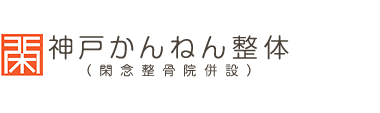第3回 【急性期】激痛を乗り切る!痛みを和らげ、悪化を防ぐ対処法
ズキズキとした痛みのピーク!「炎症」を抑え込む最重要期間
四十肩(肩関節周囲炎)の発症から数週間〜数カ月間は、痛みが最も激しい「急性期(きゅうせいき)」に当たります。
この時期は、関節の周りで炎症が活発に起こっており、安静にしていてもズキズキと疼き、特に夜間には睡眠を妨げるほどの激痛(夜間痛)に悩まされることが特徴です。
「痛いからといって動かさないと固まってしまうのでは?」と不安に感じるかもしれませんが、急性期に最も重要なのは「炎症を抑えること」であり、無理に動かすのは厳禁です。
今回は、この最もつらい急性期をいかに乗り切り、症状の悪化を防ぐか、そのための具体的な対処法と治療の基本について詳しく解説します。
🚨 急性期に「無理に動かす」のは絶対NG!
前回のブログで解説した通り、四十肩の痛みは関節の周囲に起きている「炎症」が原因です。炎症が起きている組織は、例えるなら火事のような状態です。
この火事の状態のときに、無理に動かしたり、強いマッサージをしたりすることは、「火に油を注ぐ」行為に等しく、かえって炎症を拡大させ、痛みを悪化させてしまいます。
無理に動かした結果、起こりうる悪影響:
-
炎症の悪化: 炎症組織が刺激され、痛み物質が多く放出されて痛みが強まる。
-
防御性収縮の誘発: 激しい痛みから体を守るために、肩周りの筋肉が過剰に緊張し、さらに硬くなってしまう(拘縮を早める原因になる)。
-
他の組織の損傷: 炎症部位に無理な力が加わり、微細な損傷が広がる可能性がある。
急性期は、肩をできるだけ安静に保ち、炎症を鎮めることに専念してください。
💊 痛みをコントロールする「薬物療法」と「注射」
激しい急性期の痛みを我慢し続けると、睡眠不足や精神的なストレスで、かえって痛みに敏感になってしまいます。痛みをコントロールすることは、肩を安静に保つためにも非常に重要です。
1. 痛みの飲み薬(内服薬)
整形外科で一般的に処方されるのは、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれる種類の飲み薬です。
-
役割: 痛みを感じるメカニズムに関わる物質(プロスタグランジンなど)の生成を抑え、炎症を鎮めると同時に、痛みを和らげる効果があります。
-
注意点: 痛みが強いときだけでなく、医師の指示通りに定期的に服用することで、肩の組織に持続的に炎症を抑える作用をもたらすことが重要です。
2. 外用薬(湿布や塗り薬)
-
役割: 飲み薬と同じくNSAIDsの成分が含まれており、皮膚から炎症部位に作用して痛みを和らげます。
-
使い分け: 内服薬と併用することで、より効果的に痛みを抑えることができます。
3. 注射療法(ピンポイントで炎症を鎮める)
痛みが非常に強く、特に夜間痛で眠れない場合に有効なのが注射による治療です。
-
ステロイド注射: 非常に強力な抗炎症作用を持つステロイド薬と、局所麻酔薬を混ぜて炎症の中心部に直接注入します。即効性があり、つらい夜間痛を劇的に改善できる場合があります。ただし、多用はできないため、医師とよく相談が必要です。
-
ハイドロリリース(筋膜リリース注射): 超音波(エコー)画像を見ながら、硬くなった筋肉や腱の周囲にある「筋膜」などの癒着部位に生理食塩水などを注入し、癒着を剥がして動きを改善したり、痛みを和らげたりする治療法です。特に最近注目されており、痛みの改善に有効なケースが多いです。
Point: 痛みを我慢せず、薬や注射で「眠れること」「日常生活の最低限の動作ができること」を目標に、医師と相談しながら治療を進めてください。
❄️ 急性期のセルフケア:冷却(アイシング)と安静のポジション
急性期は自宅でのセルフケアも、「炎症の鎮静」と「夜間痛の対策」に絞って行います。
1. 患部の「冷却(アイシング)」
-
目的: 炎症が活発な急性期は、熱を持っているため、冷やすことで血管を収縮させ、炎症を鎮め、痛みの感覚を麻痺させる効果(鎮痛作用)が期待できます。
-
方法:
-
ビニール袋に氷と少量の水を入れ、空気を抜いて口を閉じ、患部に当てます。(保冷剤は冷やしすぎることがあるため、タオルで包んで使用してください)
-
15分〜20分程度を目安に冷やします。冷やしすぎると凍傷の恐れがあるため注意が必要です。
-
冷やした後、少し時間(1時間程度)を空けて、痛みが強い時に繰り返します。
-
-
注意点: 慢性期に入り、痛みが和らいで肩が固まってきたら、冷やすのではなく温める「温熱療法」に切り替えるのが一般的です。今の自分の段階に合わせて適切に選択してください。
2. 最も楽な「安静のポジション」を見つける
急性期は、肩を休ませるための工夫が最も重要です。
-
日中の安静: 痛みが強い間は、三角巾やアームスリング(腕を吊るバンド)などを使用し、肩関節が動かないように固定するのも有効です。腕を下げていると肩の重みで痛む場合は、肘の下にクッションを置いたり、痛い方の腕を抱えたりして、楽な姿勢を保ちましょう。
-
夜間痛の対策(就寝時の工夫):
-
痛くない方を下にする: 痛い方の肩が圧迫されないように、必ず痛くない方を下にして横向きに寝ます。
-
抱き枕やクッションを活用: 痛い方の腕全体をクッションや抱き枕の上に優しく乗せ、肩が前に落ちないように支えます。肩関節が最も安定し、力が抜けるポジションを探しましょう。
-
背中にタオル: 仰向けに寝る場合は、背中の痛い方の肩甲骨の下に薄いタオルなどを敷き、肩をわずかに高くすることで、関節包が伸ばされすぎるのを防ぎ、痛みを軽減できる場合があります。
-
📅 急性期から慢性期への移行のサイン
急性期が終わり、慢性期へ移行するサインは、痛みの性質が変わることです。
| 状態 | 急性期(初期) | 慢性期(拘縮期) |
| 痛み | 安静にしていても痛む、ズキズキとした激痛(夜間痛あり) | 安静時は痛くない、動かしたときにのみ痛む(夜間痛は減少) |
| 可動域 | 痛みのため、動かそうとしない(自発的制限) | 痛みは減ったが、関節が固まって動かせない(拘縮) |
| 対処の優先順位 | 炎症を抑える、安静 | 固まった関節を動かす、リハビリ |
夜間痛が減り、安静時の痛みがなくなり、「動かしたときだけ痛い」という状態に変化したら、それは慢性期への移行のサインです。無理のない範囲で、次のステップであるリハビリテーションを考え始める時期が来たということです。
次回のブログでは、病院で行う「診断方法」と、急性期から慢性期にかけて選択される具体的な「治療の選択肢」について、専門家の視点を交えて詳しく見ていきましょう。
※ご相談はこちらからお気軽になさってください。
神戸かんねん整体
#股関節痛 #変形性股関節症 #膝関節痛 #変形性膝関節症 #四十肩 #五十肩 #側弯症 #O脚 #慢性腰痛 #座骨神経痛 #脊柱管狭窄症 #頸の痛み #肩こり #頭痛 #足の痛み #脚長差
神戸市東灘区御影中町6丁目4-23エスペランサ御影1F
078-846-0655