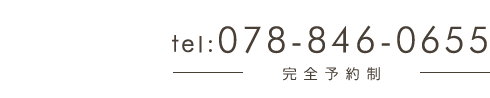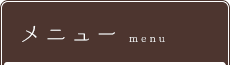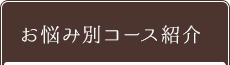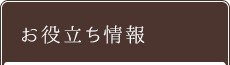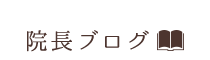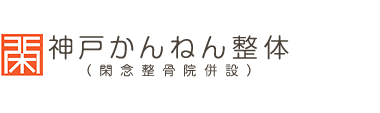第2回:痛みはどこから?-あなたの股関節が悲鳴を上げるメカニズム
前回のブログで、40代・50代女性に多い股関節痛の初期サインについてお話ししました。今回は、なぜ股関節に痛みが生じるのか、そのメカニズムについて、少し専門的な視点から解説します。
股関節の構造と役割
股関節は、私たちの身体の中で最も大きな関節の一つです。太ももの骨(大腿骨)の先端にある球状の「大腿骨頭」と、骨盤にあるお椀のような形の「臼蓋(きゅうがい)」が組み合わさってできています。この構造により、股関節は前後左右、そして回転という非常に広い可動域を持っています。
この股関節の表面は、「関節軟骨」という滑らかで弾力のある組織で覆われています。この軟骨は、骨同士が直接こすれ合うのを防ぎ、歩行や立ち上がりの際の衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。
痛みの主な原因:軟骨のすり減り
変形性股関節症の痛みの最大の原因は、この関節軟骨のすり減りです。 何らかの原因で軟骨が少しずつ摩耗していくと、クッション機能が低下します。これにより、関節に直接的な摩擦が生じ、炎症が起こり、痛みとして現れるのです。
軟骨がすり減る原因には、以下のようなものが挙げられます。
- 臼蓋形成不全(先天性股関節脱臼の後遺症): 臼蓋の形成が不十分で、大腿骨頭を十分に覆いきれていない状態です。この場合、股関節にかかる体重の負担が局所的に集中し、軟骨が早くすり減ってしまいます。日本では、これが変形性股関節症の最大の原因と言われています。
- 加齢: 軟骨は加齢とともに水分含有量が減少し、弾力性を失います。また、新陳代謝も低下するため、小さな損傷が修復されにくくなります。
- 過度な負担: 肥満、重労働、激しいスポーツなど、股関節に継続的に過剰な負担をかける生活習慣も軟骨の摩耗を加速させます。
痛みを生み出す「筋肉のアンバランス」
軟骨のすり減りだけでなく、股関節周囲の筋肉のバランスの崩れも、痛みの原因となります。
股関節を支える筋肉は、身体の安定性を保つ上で非常に重要です。
しかし、痛みがある状態では、無意識のうちに痛い方の脚をかばい、正しい筋肉が使われなくなります。 これにより、
- 特定の筋肉に過剰な負担がかかり、筋肉の緊張やこわばりが生じる
- 使われなくなった筋肉が衰え、筋力が低下する といった「筋肉のアンバランス」が起こります。
この筋肉のアンバランスは、股関節の正しい動きを妨げ、痛みをさらに悪化させる悪循環を引き起こします。たとえば、股関節を動かす際に必要な腸腰筋が硬くなると、歩幅が狭くなり、膝や腰に負担がかかるようになります。
日常生活の何気ない動作が引き起こす悪循環
日々の生活の中にも、股関節に負担をかける要因は潜んでいます。
- 脚を組んで座る癖: 骨盤が傾き、股関節に不自然なねじれが生じます。
- 横向きに寝る癖: 常に片側の股関節に体重がかかり、負担となります。
- 中腰での作業: 股関節の屈曲と伸展が不十分なままでいると、周囲の筋肉が硬くなります。
※ご相談はこちらからお気軽になさってください。
神戸かんねん整体
#股関節痛 #変形性股関節症 #膝関節痛 #変形性膝関節症 #四十肩 #五十肩 #側弯症 #O脚 #慢性腰痛 #座骨神経痛 #脊柱管狭窄症 #頸の痛み #肩こり #頭痛 #足の痛み #脚長差
神戸市東灘区御影中町6丁目4-23エスペランサ御影1F
078-846-0655